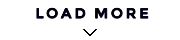LIXIL GINZA SOLO EXHIBITION
下沢敏也展-Re-birth風化から再生へ
原始、やきものは生命(いのち)あるものを生み出す力を持つ、女性にだけ許された特権であった。それは、大地から土という生命あるものを採って、新たな生命<うつわ>を生み出すことであった。いまからおよそ一万五千年前、縄文土器は北の大地の土によって誕生した。陶芸家・下沢敏也は、その壮大な時間の流れの中から、生命の記憶を探(さぐ)り出そうとしている。彼にとって陶芸とは、土の生命を創造することであり、同時に、北の大地に生きる自分自身を問うことなのかも知れない。
下沢は1960年、北海道陶芸協会の創設者・下沢土泡(どほう)の次男として生まれた。土泡の作品は、北の大地の大らかさと荒々しさとが融合する力強い作品である。土泡の作品を眺めていると、大地にしっかり根を張り生きる、土泡の壮絶な生き様が伝わってくる。
下沢は18歳で父に師事し、のち信楽で陶芸の研修をする。彼が走泥社の八木一夫、鈴木治、山田光らの作品と出合い虜になったのは、その頃のことであろう。以後、試行錯誤を繰り返しながら、独学で前衛陶芸的な作品に挑戦する。1997年には、北海道文化財団の海外派遣によりニューヨークでも研修を積んだ。その後、陶を用いて植物や布、あるいは絵画や版画、音楽とのコラボレーションを積極的に展開する。また、2003年からは北海道立体表現展に参加し、陶彫やオブジェといった概念を超えるスケールの大きいインスタレーションを試みている。
下沢が林立する柱状の立体作品を発表したのは、2009年の北海道立近代美術館で行われたインスタレーションからである。それは、柱状や円形などの極めてシンプルな形態や、原初的かつ塊量性に富んだ力強い造形によって、生命の蘇生や、その往還を象徴する作品である。以後、下沢は一貫してRe-birth<風化から再生へ>をテーマに制作している。
Re-birthとは<再生>という意味だが、下沢は「風化から再生へ向かう力、見た目はもう既に風化していっている、そんな質感を出来るだけ強調したい」という。風化は終わりではなく、始まりなのである。そのためには、出来るだけ北の大地の土を使い、「制作過程で手をかけ過ぎないことだ」という。手を掛け過ぎると、土を成型した時の表情が崩れてしまうからだ。土という素材と真摯に向き合いながら、朽ち果てていくものから生まれ変わる時間の経過を含めたRe-birth<風化から再生へ>をテーマに、下沢はこれからも挑み続けることであろう。
今展には、さらに進化した柱状の立体作品と共に、新たに取り組んでいる生の土と薄い焼成した陶板を融合させた平面作品も展示される。
森 孝 一 (美術評論家・日本陶磁協会常任理事)



![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170001_3821.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170026_0722.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170058_2523.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170128_9963.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170143_2926.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170203_5652.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170230_6668.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170329_6161.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170351_8162.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170415_9496.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170431_3838.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170504_4551.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170524_6723.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170539_5455.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170556_3409.jpg)
![札幌美術展 [下沢敏也 Origin-土の命脈] 2025.9.13~11.3 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2026_0101_170630_7654.jpg)
![[Simozawa Tosiya Origin-土の命脈] 札幌芸術の森美術館 2025,9.13~11,3](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1210_202034_5007.jpg)
![[Simozawa Tosiya Origin-土の命脈] 札幌芸術の森美術館 2025,9.13~11,3](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1210_202053_1999.jpg)
![北海道新聞掲載記事 [札幌美術展 下沢敏也 Origin-土の命脈] 札幌芸術の森美術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_124110_5012.jpg)
![下沢敏也展 [Re-birth2025 沈黙の始まり Ⅲ] ギャラリー創 7月26日〜8月10日](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_123018_9286.jpg)
![下沢敏也展 [Re-birth2025 沈黙の始まり Ⅲ] ギャラリー創 7月26日〜8月10日](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_123116_7794.jpg)
![下沢敏也展 [Re-birth2025 沈黙の始まり Ⅲ] ギャラリー創 7月26日〜8月10日](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_123152_5450.jpg)
![下沢敏也展 [Re-birth2025 沈黙の始まり Ⅲ] ギャラリー創 7月26日〜8月10日](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_123257_8469.jpg)
![下沢敏也展 [Re-birth2025 沈黙の始まり Ⅲ] ギャラリー創 7月26日〜8月10日](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_1209_123323_4691.jpg)
![下沢 敏也展 風化から再生2024 [朽ち往くものから] 2024.10.12~12.8 北海道立釧路芸術館・](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_0601_101203_0610.jpg)
![下沢 敏也展 風化から再生2024 [朽ち往くものから] 2024.10.12~12.8 北海道立釧路芸術館・](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_0601_101238_0823.jpg)
![下沢 敏也展 風化から再生2024 [朽ち往くものから] 2024.10.12~12.8 北海道立釧路芸術館・](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_0601_101258_9384.jpg)
![下沢 敏也展 風化から再生2024 [朽ち往くものから] 2024.10.12~12.8 北海道立釧路芸術館・](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2025_0601_101325_4003.jpg)



![下沢敏也展 ”series Re-birth 風化から再生2024[朽ち往くものから]” 北海道立釧路芸術館](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2024_1002_083521_4521.jpg)









![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0805_101211_9598.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093120_8491.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093150_6854.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093206_3765.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093225_0205.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093250_1104.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093311_2160.jpg)
![Re-birth 2022 [沈黙の栖]-The gathering of silence-](https://s3.media-nisor.site/image_thumbs/toshiyashimozawa_entry_2022_0810_093337_0857.jpg)